
WAnocoto着付けレッスン講師 早見 由美子さん
一番大切なことは、喜びの気持ちを装いに込めるということ。マナーとは、誰かに喜んでもらったり、お祝いの気持ちを伝えたりするためのもので、決して怖いものではありません。そこをおさえて、なおかつ自分が着ていて嬉しいものを選べれば大丈夫。自身の立場や会場の格によっても少し変わりますので、ふさわしい一着を選んで、楽しく過ごしてくださいね。

華やかでどこかおめでたい印象も与える着物は、結婚式に着て行ったら喜ばれる服装の一つですよね。でも、気になるのが、着物に関するマナー。どんな種類を選べばいいのか、気を付ける振る舞いなどはないか、「和のレッスンスタジオWAnocoto」講師の早見さんに教えてもらいました。

一番大切なことは、喜びの気持ちを装いに込めるということ。マナーとは、誰かに喜んでもらったり、お祝いの気持ちを伝えたりするためのもので、決して怖いものではありません。そこをおさえて、なおかつ自分が着ていて嬉しいものを選べれば大丈夫。自身の立場や会場の格によっても少し変わりますので、ふさわしい一着を選んで、楽しく過ごしてくださいね。
#01 結婚式に着て行ける着物は?
└ 黒留め袖に袋帯
└ 色留め袖に袋帯
└ 振り袖に袋帯
└ 訪問着に袋帯
└ 付け下げに袋帯
#02 結婚式の着物姿でのマナーでおさえておくべきことはある?
#03 着物着用時の立ち居振る舞いマナー
結婚式は式典としての場でもあるため、##s##お祝い感のある華やかさとともに、きちんとした装い##e##が求められます。##s##着物そのものに「格」というものがあり、年齢や新郎新婦との関係性・立場によっても着ていくものが変わります##e##。
そこで、まずは参列者が着ていける着物をご紹介するとともに、それらの特徴や、どんな人が着るのにふさわしいか、しっかり見ていきましょう。

##s##背に1つ、両袖の後ろと両胸に1つずつの合計5つの家紋(五つ紋)を入れる##e##のが決まりの、##s##地色が黒##e##の着物。生地には##s##地模様のないちりめん##e##を用いて、##s##裾部分にのみ模様が入っている##e##のが特徴。##s##既婚女性が着る着物の中で最も格が高い##e##。
新郎新婦の母、媒酌人夫人、身内の既婚女性
模様が大きい方が若い人向け。また、慶びを願う吉祥文様の中でも##s##鶴や亀、松竹梅など格のある柄を選ぶと、より格調の高い印象##e##に。

##s##地模様がなく地色が色もので、裾周りにのみ柄があり、家紋を入れた着物##e##。色留め袖の紋が1~3つの場合は準礼装となり、5つの場合は最も格の高い正礼装として、黒留め袖と同じ格になる。
未婚・既婚問わず着ることができる。新郎新婦の姉妹、親族、ゲスト
着物をレンタルする場合、##s##誰が使用してもよい家紋(通紋)が入っている##e##ので、実家や嫁ぎ先の家紋が入っていなくてもOK。

袖の長い##s##未婚女性の正礼装##e##。
姉妹、親族、友人などの未婚のゲスト
##s##花嫁の衣裳とされる大振り袖は避け、中振り袖や小振り袖を選ぶ##e##のがおすすめ。ちなみに成人式で着るのは中振り袖が多い。また、小物合わせや帯結びで年齢に合わせた雰囲気を出せる。

##s##未婚、既婚問わず女性の準礼装##e##。着物全体で一つの絵のように表現された華やかな絵羽模様が描かれている。
親族、友人
##s##親族として参列する場合は、格が高く、古典柄を中心とした落ち着いた色合いがベスト##e##。友人は明るめの色を選んで花を添えるなど、年齢や立場に応じた装いに同等格の小物を合わせる。

##s##訪問着に準ずる略礼装##e##。訪問着の模様付けを簡略にしたよそ行きの着物。
親族、友人
最近は訪問着と見分けにくい華やかなタイプも多いので##s##「豪華orシンプル」を好みで選んでもOK##e##。

色無地……##s##黒以外の色一色で柄のない着物##e##。紋が1つ以上入ると準礼装となる。
江戸小紋……一見無地に見えるが、##s##細かい一色染めの柄が入ったもの。格が高い柄を選ぶと色無地と同格##e##となり、1つ以上紋を入れると準礼装となる。
小紋……##s##同じ模様がパターンで描かれている着物##e##。吉祥文様や古典柄の場合は、結婚式でも着ることができる。
友人、同僚などのゲスト
訪問着や付下げよりもシンプルな印象になるので、##s##地味になりすぎないよう帯回りを華やかに##e##。
着物の装いは##s##帯や小物、草履、バッグなど全体の格をそろえることが大切##e##。とはいえ、難しく考えず、年齢や自分のキャラクターを生かした、華やかな上品さを心掛けましょう。
##s##ピアスやネックレスなどのアクセサリーや時計は着けないのが全体のバランスもよく、スマート##e##な印象。何か合わせる場合は、かんざしなどの髪飾りで花を添えて。

##s##ミディアムヘアからロングヘアの場合はうなじがすっきり見えるアップスタイルがおすすめ##e##。首すじを見せるとすっきり美しい印象になります。##e##ショートヘアの場合は、着物の華やかさとバランスが取れるように、トップに適度なボリュームを出す##ee##のもよいでしょう。髪飾りは、かんざしや小ぶりなモチーフなど、上品さを意識してセレクトを。
身体全体を1枚の布で包み込むような着物は、腕も足元も小さめに動かすと着崩れが防げます。##s##ゆったりと小ぶりな動きを心掛けて##e##。着物だからといってマナーを気にし過ぎず、次のことをを心掛けていれば大丈夫。安心して楽しみましょう。
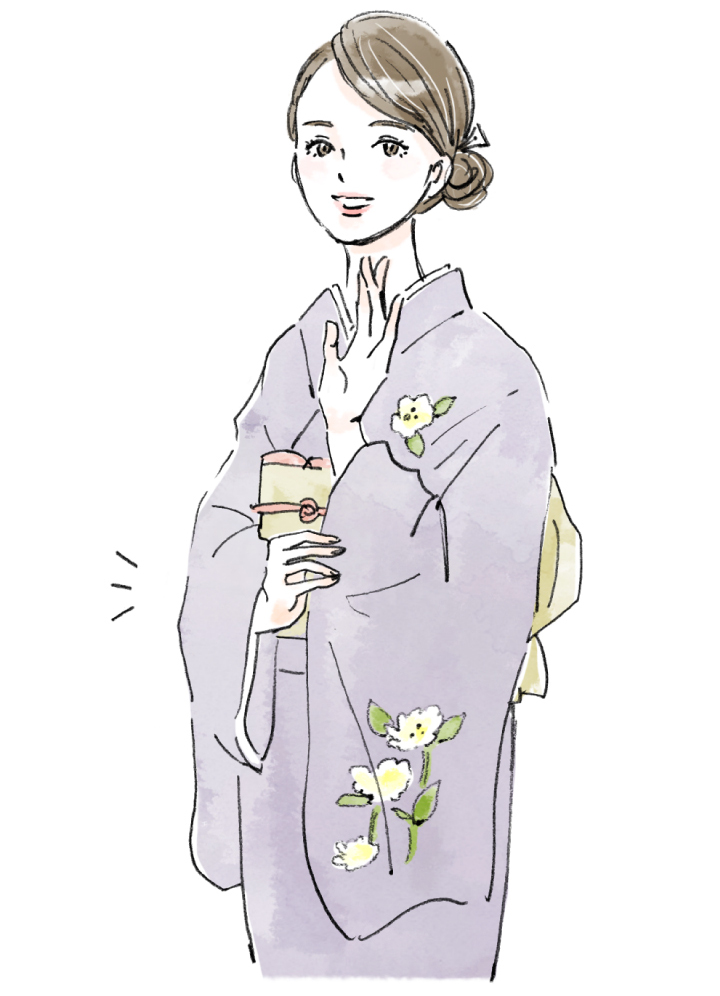
背筋を伸ばし、反対の手で袖口を押さえるなど、##s##袂(たもと)の存在を忘れずに##e##。
##s##上前(うわまえ)が崩れぬよう、手を添える##e##ように気を付けて。階段を上り下りする際も同様に。
前だけでなく、##s##後ろ姿の着崩れの確認##e##も忘れずに。
その他の服装や持ち物についても確認しよう
結婚式にお呼ばれした時、意外に迷ってしまうのが「服装」と「持ち物」。お祝いの場にふさわしい結婚式の服装について、マナーデザイナー 岩下宣子先生が詳しく解説します。
結婚式に招待されたとき、多くの女性が頭を悩ませるのは「何を着ていくか?」ということではないでしょうか。マナーデザイナーの岩下宣子先生に、お祝いの席にふさわしいお呼ばれ服のポイントについて伺いました。

早見由美子 WAnocoto着付けレッスン講師
着物好きの祖母、母の影響で幼い頃から着物に触れて育つ。21歳で着付け講師資格を取得。以後、仕事や家庭のかたわら、自宅やカルチャーセンターなどで着物の楽しさを伝える活動を行う。2011年よりWAnocotoで着付け講師として着付けレッスンやきものの知識レッスンなどを担当。
【和のレッスンスタジオWAnocoto】
http://www.wanocoto.com
2020年4月上旬には、茶室を併設したエクスペリエンス型の着物ショップ「WAnocoto mono」がオープン予定
構成・文/小松七恵 イラスト/nodeko

 結婚準備完ぺきマニュアル
結婚準備完ぺきマニュアル