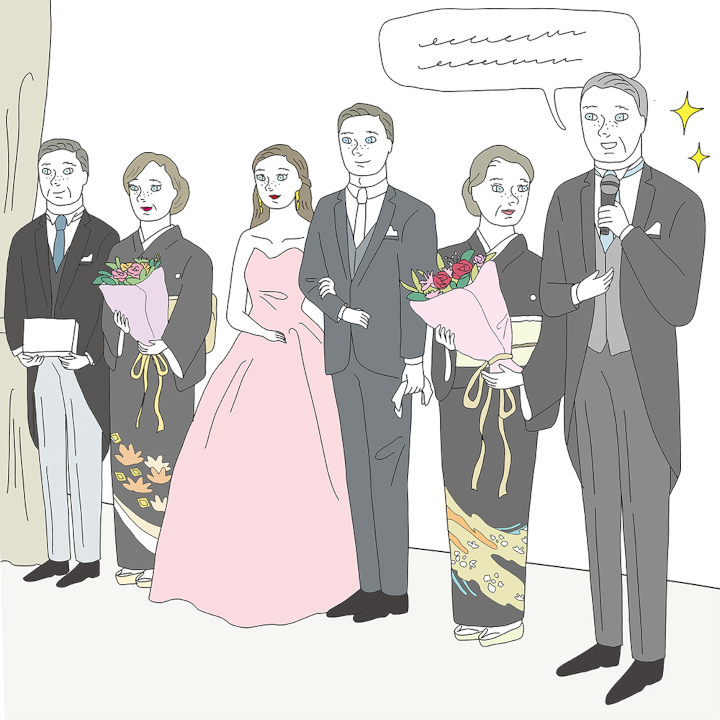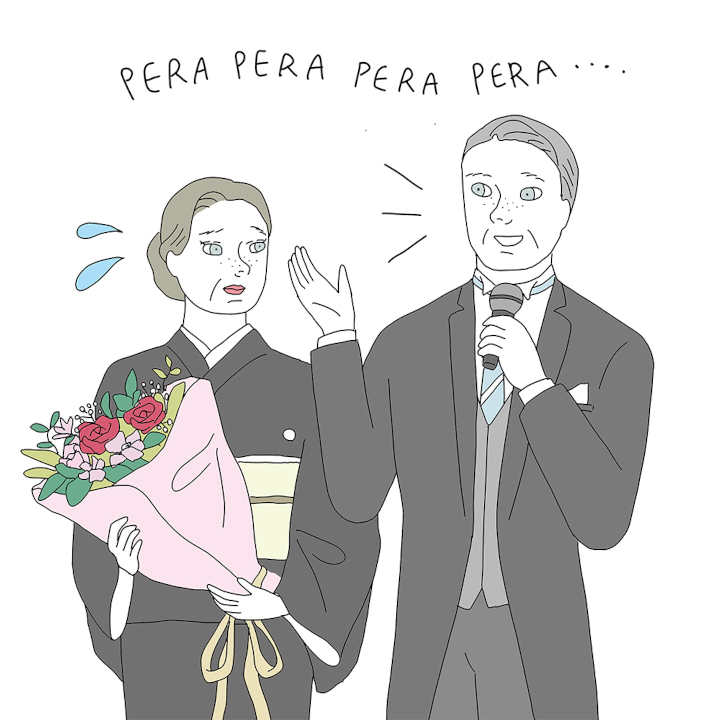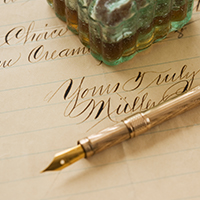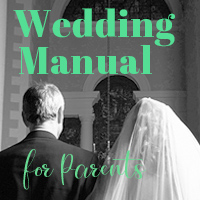Wedding Manual for Parents
結婚式の【親の謝辞】完全マニュアル|そのまま使える文例付き!
両家が並んでゲストに感謝の気持ちを伝え、披露宴はいよいよお開きへ…。ここでは締めくくりにふさわしい「親の謝辞」について、一般的な構成の解説と、そのまま使える文例を交えて紹介します。
#01|親の謝辞とは?
ゲストに感謝の気持ちを伝えるのが目的
簡潔にまとめましょう
披露宴ではお開きを迎える前に、##s##両家を代表していずれかの親が謝辞を述べるのが一般的##e##です。役割を担うのは新郎側の父が多いのですが、もちろん状況によっては新婦側の父やいずれかの母が務めても構いません。
最近では、親御さんに代わって新郎が謝辞を引き受けたり、親の謝辞とは別に決意を述べたりするようになってきました。親御さんとしては、出席してくださったゲストへの感謝と、「ふたりをよろしくお願いします」という思いを言葉にして伝えたいものです。
親の謝辞の基本構成と長さの目安
##s##長い謝辞を述べる必要はなく、できるだけ簡潔にまとめます##e##。1~2分程度のあいさつでも十分です。暗記するのが不安ならメモを持ち込んでも問題ありませんので、気構えずに落ち着いて臨みましょう。
親の謝辞の基本構成と文例
オーソドックスな謝辞の構成はパーツで分けることができます。
まず「出だし」の言葉から始まって、次にゲストへの「感謝」を述べ、続いて今後ともふたりを見守ってほしいとの「お願い」をし、ラストは「締め」の言葉です。
この4つのパーツを組み合わせながら考えると意外と簡単。そして文例集を参考にしつつ、少しだけオリジナルのアレンジを加えてみてはいかがでしょう。
構成1 出だし
最初が肝心です。親御さんからゲストへの「感謝の気持ちを込めたあいさつ」となっていれば問題ありません。
文例:
ただいまご紹介にあずかりました新郎の父、山田志郎でございます。
山田家、大西家を代表いたしまして、お礼のごあいさつを申し上げます。
構成2 感謝の言葉
ふたりを祝福するために披露宴に集まってくださった一人一人に対して、感謝の気持ちを伝えます。
文例:
本日はお忙しい中、大勢の皆さまにご臨席を賜り、深く御礼申し上げます。
先ほどより新郎新婦に対し、温かい励ましのお言葉をいただきまして、感謝の気持ちでいっぱいでございます。
構成3 依頼の言葉
まだまだ未熟なふたり。そんなふたりをこれからも支え、導いてほしいとの願いを込めた言葉を。
文例:
なにぶん、まだ未熟なふたりでございますが、どうぞこれからも皆さま方のお力添えを賜り、温かく見守っていただければと思います。
構成4 締めの言葉
ゲストの健康とご多幸を祈る言葉を添え、親御さんからの感謝の気持ちを再度織り交ぜつつ、締めましょう。
文例:
はなはだ簡単ではございますが、両家を代表し、これにてお礼の言葉とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
#02|親の謝辞で気を付けること&忌み言葉
お祝いの場に
ふさわしい内容であることが大前提
忌み言葉が含まれていないかもチェック
スピーチで避けたい話題
タブー1 新郎・新婦の失敗談や短所に触れる内容ではありませんか?
へりくだって「未熟なふたり」という言い回しを使うことは問題ありませんが、##s##新郎・新婦の評判を下げるような話はタブー##s##です。
タブー2 自分自身や家族の自慢話が中心になっていませんか?
謝辞はあくまでも「ゲストに感謝の気持ちを伝える」スピーチです。##s##父親自身や家族の話はここでは我慢をし、簡潔に感謝のスピーチを述べる##e##と披露宴の最後がグッと締まります。
結婚式でタブーとされる“忌み言葉”
おめでたい結婚式では、縁起が悪い「忌み言葉」を避けるのが常識です。
うっかりスピーチで使わないよう気を付けつつ、原稿を作成しましょう。
caution! 再婚を連想させる言葉
【重ね言葉】重ね重ね/重々/次々/たびたび/しばしば/くれぐれも
【再婚を連想】繰り返し/再び/戻る
caution! 不幸を連想させる言葉
苦しい、悲しい、忘れる、負ける、衰える、色あせる、病気、亡くなる、涙、泣く、滅びる、しめやかに、悪い
caution! 夫婦の別れを連想させる言葉
別れる、離れる、終わる、切れる、割れる、破れる、壊れる、捨てる、去る、消える、なくす、流れる、ほどける
#03|事前に確認しておくことは?
新郎の謝辞とバッティングしないよう
事前確認を
披露宴ではゲストへの感謝を込めて、両家を代表する親の謝辞で締めくくるのが基本です。ただし最近では新郎自ら謝辞を述べるケースも増えてきました。
それぞれあいさつを行う場合は、基本的には親→新郎の順番です。感謝を伝えるという点に関してはいずれの謝辞も一緒ですが、親が「ふたりの今後を託す」という内容を盛り込むのに対し、新郎は「自らの抱負」を述べるという点が大きく異なります。##s##新郎と話す内容が極力重ならないように、新郎と事前に内容の擦り合わせをしておくと安心##e##です。
#04|組み合わせてそのまま使える
親の謝辞文例
1「出だしの言葉」文例
出だしは今日の天候や披露宴の様子、ゲストの顔触れなどに合わせて変化を付けてみてはいかがでしょう。オリジナリティーに加え、親ならではの気配りも伝えられそうです。
新郎の父・山田志郎と申します。本日は新郎新婦のために多くの皆さまにお集まりいただきましたことを、両家を代表し、心より感謝申し上げます。
両家を代表し、新郎の父・山田志郎よりごあいさつを述べさせていただきます。本日はあいにくの空模様にもかかわらず、ご出席いただきまして誠にありがとうございました。
ただいまご紹介にあずかりました新郎の父・山田志郎でございます。本日、無事にこの日を迎えることができ、感無量の思いでいっぱいです。
2「感謝の言葉」文例
「皆さまがいてくださっての新郎新婦」という感謝の気持ちを、自分が最も伝えやすい言葉で。祝辞を頂いた際などに感じた思いを盛り込むと、さらに深みが出るでしょう。
本日はあいにくの空模様にもかかわらず、このように多くの皆さまにご臨席を賜り、深くお礼を申し上げます。先程からの多くの方々からのご祝辞や、温かい励ましのお言葉、親としても身に余る光栄でございます。
新郎・孝二郎が、このように素晴らしいはるかさんという生涯の伴侶を得て、今日の良き日を迎えられましたことも、ひとえに本日お集まりの皆さま方の、温かい励ましとお力添えの賜物だと心より感謝申し上げます。
皆さま方にはお忙しい中、ふたりのためにお集まりいただきまして、あらためてお礼を申し上げます。また、媒酌の労をおとりいただいた○○様ご夫妻(仲人がいる場合)にも厚く御礼申し上げます。
3「依頼の言葉」文例
「こういう家庭を築いていってほしい」という親としての思いを含め、ゲストにふたりを温かく見守ってほしい旨を伝えましょう。親の愛がひしひしと伝わる文面だとベストです。
至らぬところばかりのふたりでございます。勝手なお願いではございますが、どうかこれからも温かく見守り、叱咤(しった)激励いただけると幸いです。
本日晴れて夫婦となったふたりですが、これから新しい家庭を築いていく道のりは決して平坦ではないでしょう。今後とも皆さま方のご指導・ご鞭撻(べんたつ)を賜りたいと思っております。
本日、新しい人生のスタート地点に立ったふたりですが、親の目から見ればまだ未熟で心もとないものがあります。ぜひとも皆さまのお力添えを頂戴したく存じます。
4「締めの言葉」文例
ラストは自分が一番言いやすいフレーズを使うと安心です。途中の言葉が多少詰まったとしても、締めくくりがきちんとしていれば、親御さんの思いも必ずゲストに伝わることでしょう。
ご臨席の皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。
本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。
本日は慣れない宴席で不行き届きの面も多々あったと思いますが、何卒お許しくださいませ。結びに皆さまのご健康とご多幸を願いつつ、両家代表のあいさつと代えさせていただきます。
この後、新郎・孝二郎にもあいさつをさせますが、まずは両家を代表いたしまして、私より皆さま方へのお礼の言葉とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
このカテゴリの関連記事
イラスト/moko. 構成・文/小田真穂(編集部)