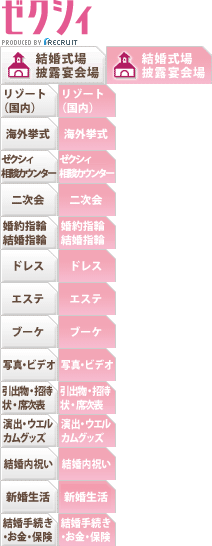出雲記念館 ●IZUMO GROUP
福井駅/福井駅より車で10分、北陸自動車道福井ICより車で25分
アクセス/TEL
- この会場が気になったらブライダルフェア一覧へ
- フェア参加が難しい方は電話で見学予約
- クリップする
-
クリップ済み
クリップ一覧に追加しました
カテゴリ
出雲大社についての記事一覧
神社コラム・069◆節分の大護摩供養
更新:2017/1/29 13:47
出雲大社福井分院では2月2日(木)・3日(金)の両日、
節分大祭をとり行います。
同時に、期間中は大鳥居よこに護摩(ごまどう)堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩供養(ごまくよう)を行っております。

護摩(ごま)とは、
護摩木(ごまき)と呼ばれる木の棒をを神仏に捧げて燃やすことで、
それぞれのお祈りごとを天へ届けることです。
護摩木には祈願者の氏名・住所・年齢(数え年)・祈願内容を記します。
厄年の方は特に厄除として供養しますので、
年齢(数え年)はとても重要です。
よろしければ参考にこちらもご覧ください。
→神社コラム・027◆厄年のおはらいをした方がいい理由
→神社コラム・028◆数え年のふしぎ
護摩供養には多くの流派があり、作法もさまざまですが、
出雲大社福井分院では、古くからお祀りしている
お不動さん(不動明王)に対してお経や真言を捧げます。
→神社コラム・053◆出雲大社のお不動さん
護摩木は社務所でお授けしているほか、
節分大祭の両日中でも受け付けておりますので、
どうぞお越しください。

あらためて節分大祭のご案内を。
出雲大社福井分院では2月2日(木)・3日(金)の両日、
節分大祭をとり行います。
期間中は大鳥居よこに護摩堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩神事を行っております。
また3日(金)は毎年恒例の豆まきも行います。
豆袋とたくさんのお菓子をまく上、豆袋に「当たりくじ」がある方には
豪華プレゼントも。
年に一度のお楽しみ行事、どうぞ皆さまお越しください。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
節分大祭をとり行います。
同時に、期間中は大鳥居よこに護摩(ごまどう)堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩供養(ごまくよう)を行っております。

護摩(ごま)とは、
護摩木(ごまき)と呼ばれる木の棒をを神仏に捧げて燃やすことで、
それぞれのお祈りごとを天へ届けることです。
護摩木には祈願者の氏名・住所・年齢(数え年)・祈願内容を記します。
厄年の方は特に厄除として供養しますので、
年齢(数え年)はとても重要です。
よろしければ参考にこちらもご覧ください。
→神社コラム・027◆厄年のおはらいをした方がいい理由
→神社コラム・028◆数え年のふしぎ
護摩供養には多くの流派があり、作法もさまざまですが、
出雲大社福井分院では、古くからお祀りしている
お不動さん(不動明王)に対してお経や真言を捧げます。
→神社コラム・053◆出雲大社のお不動さん
護摩木は社務所でお授けしているほか、
節分大祭の両日中でも受け付けておりますので、
どうぞお越しください。

あらためて節分大祭のご案内を。
出雲大社福井分院では2月2日(木)・3日(金)の両日、
節分大祭をとり行います。
期間中は大鳥居よこに護摩堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩神事を行っております。
また3日(金)は毎年恒例の豆まきも行います。
豆袋とたくさんのお菓子をまく上、豆袋に「当たりくじ」がある方には
豪華プレゼントも。
年に一度のお楽しみ行事、どうぞ皆さまお越しください。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・068◆節分大祭・春をむかえるお祭り
更新:2017/1/28 12:05
年が明けて正月を迎えると、
あっという間に、次は節分ですね。
節分とは字のごとく、<季「節」の「分」かれめ>というのが
本来の意味合いです。
昔は季節が変わる立春・立夏・立秋・立冬の前日をさして
節分と言っていましたが、
現在では特に立春の前日をさして節分と言うようになりました。

冬という言葉は「殖ゆ(ふゆ)」から来ており、
土の中や樹木の中、目に見えないところで生命が息づき、
めぐみを「殖やして(ふやして)」いる季節をさします。
この生命が芽生え、「張る(はる)」のが、
すなわち春というわけですね。
節分は芽生えの春を迎えるための大切な区切りなのです。

なお、出雲大社福井分院では2月2日(木)・3日(金)の両日、
節分大祭をとり行います。
期間中は大鳥居よこに護摩堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩神事を行っております。
また3日(金)は毎年恒例の豆まきも行います。
豆袋とたくさんのお菓子をまく上、豆袋に「当たりくじ」がある方には
豪華プレゼントも。
年に一度のお楽しみ行事、どうぞ皆さまお越しください。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
あっという間に、次は節分ですね。
節分とは字のごとく、<季「節」の「分」かれめ>というのが
本来の意味合いです。
昔は季節が変わる立春・立夏・立秋・立冬の前日をさして
節分と言っていましたが、
現在では特に立春の前日をさして節分と言うようになりました。

冬という言葉は「殖ゆ(ふゆ)」から来ており、
土の中や樹木の中、目に見えないところで生命が息づき、
めぐみを「殖やして(ふやして)」いる季節をさします。
この生命が芽生え、「張る(はる)」のが、
すなわち春というわけですね。
節分は芽生えの春を迎えるための大切な区切りなのです。

なお、出雲大社福井分院では2月2日(木)・3日(金)の両日、
節分大祭をとり行います。
期間中は大鳥居よこに護摩堂をもうけ、
厄除けや各種祈願を奉修する護摩神事を行っております。
また3日(金)は毎年恒例の豆まきも行います。
豆袋とたくさんのお菓子をまく上、豆袋に「当たりくじ」がある方には
豪華プレゼントも。
年に一度のお楽しみ行事、どうぞ皆さまお越しください。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・067◆大寒の禊・滝行
更新:2017/1/27 18:28
雪の降る寒い日が続きますが、
皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。
暦の上では1月20日から「大寒」にあたり、
一年で最も寒さの厳しい時期といわれています。
この大寒から一週間、
出雲大社福井分院では毎年
滝に打たれて身を清める滝行を行っています。
神さまは汚れやけがれを嫌い、
清らかなことを好むとされます。
そのため神社に仕えるものは心身を清めなければいけませんが、
これを禊(みそぎ)といい、
滝行はその一種です。
ちなみに、
神社の入り口で手水をするのも禊の一種で、
ほかにも力士が土俵で塩をまいたり、
飲食店で入り口に盛り塩をするのもこの禊の役割があります。
こちらもご覧ください。
→神社コラム・004◆手水で身も心もきれいに
行の最中は滝の中で無心になって唱え事をささげます。
また滝行を行う一週間は肉や玉子、酒などを摂らない、
刃物を肌にあてない、といった制限もあります。
一週間、身を清める毎日が続きます・・・。

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。
暦の上では1月20日から「大寒」にあたり、
一年で最も寒さの厳しい時期といわれています。
この大寒から一週間、
出雲大社福井分院では毎年
滝に打たれて身を清める滝行を行っています。
神さまは汚れやけがれを嫌い、
清らかなことを好むとされます。
そのため神社に仕えるものは心身を清めなければいけませんが、
これを禊(みそぎ)といい、
滝行はその一種です。
ちなみに、
神社の入り口で手水をするのも禊の一種で、
ほかにも力士が土俵で塩をまいたり、
飲食店で入り口に盛り塩をするのもこの禊の役割があります。
こちらもご覧ください。
→神社コラム・004◆手水で身も心もきれいに
行の最中は滝の中で無心になって唱え事をささげます。
また滝行を行う一週間は肉や玉子、酒などを摂らない、
刃物を肌にあてない、といった制限もあります。
一週間、身を清める毎日が続きます・・・。

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・066◆出雲大社の左義長祭(どんど焼き)
更新:2017/1/25 16:09
左義長祭(どんど焼き)といえば
お正月の恒例神事のひとつですが、ご存知でしょうか。
正月15日ごろに全国的に行われる火祭りで、
正月の松かざりや注連縄、古いお札やお守り、絵馬などを集め、
お焚き上げをする神事です。
皆さんのお近くの神社や自治体などでも
行われたのではないでしょうか。
参考にこちらもご覧ください。
→神社コラム・015◆お守りには期限がある?

出雲大社福井分院では、
去る1月14日にこの左義長祭(どんど焼き)おこないました。
お焚き上げの前に、神主によるお祓いをします。

当日はあいにくの雪になりましたが、
一日を通して多くの方が松かざりやお守りをお持ちになられました。

お焚き上げはお守りやお札に宿った神様を
天にお返しするとともに、
それらにこめたお祈りごとを天に届ける、といった意味合いがあります。

左義長祭(どんど焼き)の炎で、
皆さまのお祈りごと・お願い事が天に届きますように・・・。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
お正月の恒例神事のひとつですが、ご存知でしょうか。
正月15日ごろに全国的に行われる火祭りで、
正月の松かざりや注連縄、古いお札やお守り、絵馬などを集め、
お焚き上げをする神事です。
皆さんのお近くの神社や自治体などでも
行われたのではないでしょうか。
参考にこちらもご覧ください。
→神社コラム・015◆お守りには期限がある?

出雲大社福井分院では、
去る1月14日にこの左義長祭(どんど焼き)おこないました。
お焚き上げの前に、神主によるお祓いをします。

当日はあいにくの雪になりましたが、
一日を通して多くの方が松かざりやお守りをお持ちになられました。

お焚き上げはお守りやお札に宿った神様を
天にお返しするとともに、
それらにこめたお祈りごとを天に届ける、といった意味合いがあります。

左義長祭(どんど焼き)の炎で、
皆さまのお祈りごと・お願い事が天に届きますように・・・。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
北陸最大級の大しめ縄の下
更新:2017/1/2 10:32
出雲記念館 記念日コンシェルジュです。
皆さま 新年あけましておめでとうございます。
大みそかから1月1日 そして本日と 晴天に恵まれ
隣接する出雲大社 福井分院も多くの初詣の方で
にぎわっております。
出雲大社 福井分院では 新年を迎えるにあたり
毎年12月23日に 島根県より大しめ縄を運んで頂き
取り替えて 新年を迎えております。
北陸最大級の大しめ縄の下 縁結びの神様に
ご参拝は、いかがでしょうか?
IZUMO GROUPでは 和魂祭と題して 1月1日~9日新春ブライダルフェアも
開催しております。 初詣がてらに ぜひ お気軽にお越しくださいませ。

皆さま 新年あけましておめでとうございます。
大みそかから1月1日 そして本日と 晴天に恵まれ
隣接する出雲大社 福井分院も多くの初詣の方で
にぎわっております。
出雲大社 福井分院では 新年を迎えるにあたり
毎年12月23日に 島根県より大しめ縄を運んで頂き
取り替えて 新年を迎えております。
北陸最大級の大しめ縄の下 縁結びの神様に
ご参拝は、いかがでしょうか?
IZUMO GROUPでは 和魂祭と題して 1月1日~9日新春ブライダルフェアも
開催しております。 初詣がてらに ぜひ お気軽にお越しくださいませ。

この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・065◆注連縄(しめなわ)取り換え
更新:2016/12/25 15:37
12月23日には出雲大社福井分院の年末恒例行事、
本殿前の大注連縄取り換えをおこないました。

新しい年を迎えるに当たり、新しい注連縄で霊力を一新し
お力をいただくための恒例行事です。
まずは一年間本殿を守り続けてくれた古い注連縄のお祓いを行います。

その後、地域の氏子さんや出雲大社の奉賛会・青壮年会の皆さん、
また出雲記念館のスタッフも揃って
一年間お世話になった大注連縄を取り外します。

そしてはるばる島根県からやってきた新しい大注連縄を
神殿前まで運びます。
大注連縄の重量は約1トン、皆の表情にも力が入ります。

神殿前へもって上がると
紐を結わえ付けて、皆で声を合わせて引き上げます。


最後に紙垂(しで)を取り付けて、完成しました。

新しい注連縄で、御参拝の皆様をお待ちしております。
初詣はどうぞ出雲大社福井分院へ。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
本殿前の大注連縄取り換えをおこないました。

新しい年を迎えるに当たり、新しい注連縄で霊力を一新し
お力をいただくための恒例行事です。
まずは一年間本殿を守り続けてくれた古い注連縄のお祓いを行います。

その後、地域の氏子さんや出雲大社の奉賛会・青壮年会の皆さん、
また出雲記念館のスタッフも揃って
一年間お世話になった大注連縄を取り外します。

そしてはるばる島根県からやってきた新しい大注連縄を
神殿前まで運びます。
大注連縄の重量は約1トン、皆の表情にも力が入ります。

神殿前へもって上がると
紐を結わえ付けて、皆で声を合わせて引き上げます。


最後に紙垂(しで)を取り付けて、完成しました。

新しい注連縄で、御参拝の皆様をお待ちしております。
初詣はどうぞ出雲大社福井分院へ。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・064◆年の始めのためしとて
更新:2016/12/22 19:46
年の瀬も迫って、皆さん忙しい毎日を送っておられることと思います。
正月ももうすぐですね。
正月でイメージされるものは色々ありますが、
「年の始めのためしとて~」
このフレーズにおぼえはありませんか?
某新春恒例番組のテーマ曲として長年使われてきたこともあり、
多くの人が一度は耳にしたことがあるかと思います。

曲のタイトルは「一月一日」。
「いちがつ ついたち」ではなく、「いちげつ いちじつ」が正しい読み方です。
実はこの曲の作詞は、
出雲大社第80代出雲国造(いずもこくそう・出雲大社のトップ)であった
千家尊福(せんげたかとみ)公によるものです。
島根の出雲大社の神楽殿横にはこの一月一日を刻んだ歌碑が設けられています。

小学唱歌として明治から戦前にかけて親しまれてきた曲で、
戦前の小学生は「君が代」などと共に、
新年の式典の際にこの「一月一日」を唄ってきました。

参考までに歌詞を掲載します。
一月一日
作詞:千家尊福 作曲:上眞行
【一番】
年の始めの ためしとて
終りなき世の めでたさを
松竹(まつたけ)立てて 門(かど)ごとに
祝ふ今日こそ たのしけれ
【二番】
初日の光 さし出でて
四方(よも)に輝く 今朝の空
君がみかげに たぐへつつ
仰ぎ見るこそ 尊(と)ふとけれ
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
正月ももうすぐですね。
正月でイメージされるものは色々ありますが、
「年の始めのためしとて~」
このフレーズにおぼえはありませんか?
某新春恒例番組のテーマ曲として長年使われてきたこともあり、
多くの人が一度は耳にしたことがあるかと思います。

曲のタイトルは「一月一日」。
「いちがつ ついたち」ではなく、「いちげつ いちじつ」が正しい読み方です。
実はこの曲の作詞は、
出雲大社第80代出雲国造(いずもこくそう・出雲大社のトップ)であった
千家尊福(せんげたかとみ)公によるものです。
島根の出雲大社の神楽殿横にはこの一月一日を刻んだ歌碑が設けられています。

小学唱歌として明治から戦前にかけて親しまれてきた曲で、
戦前の小学生は「君が代」などと共に、
新年の式典の際にこの「一月一日」を唄ってきました。

参考までに歌詞を掲載します。
一月一日
作詞:千家尊福 作曲:上眞行
【一番】
年の始めの ためしとて
終りなき世の めでたさを
松竹(まつたけ)立てて 門(かど)ごとに
祝ふ今日こそ たのしけれ
【二番】
初日の光 さし出でて
四方(よも)に輝く 今朝の空
君がみかげに たぐへつつ
仰ぎ見るこそ 尊(と)ふとけれ
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・063◆神社の音・五(拍手)
更新:2016/12/7 13:39
神社の音や音楽に関するお話をさせていただいています。
○神社コラム・059◆神社の音・壱
○神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
○神社コラム・061◆神社の音・参(竜笛)
○神社コラム・062◆神社の音・四(鈴)
こちらもご覧ください。
皆さん神社でお参りをするときに、手を合わせて、ぱんぱんと打ちますよね。
これを柏手(かしわで)と呼びます。

お寺でお参りする時は、合掌(がっしょう)して音をたてませんが、
神社では手を打つのが作法です。
かつては、手を打つことで貴人に対する敬意を表していたのが
神社の拝礼作法として伝わったとも言われています。
手を打つ回数は2回が一般的ですが、出雲大社では4回打つのが作法です。
こちらに関しては過去の記事もご覧ください。
〇神社コラム・008◆出雲大社の四拍手
〇神社コラム・009◆続・出雲大社の四拍手

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
○神社コラム・059◆神社の音・壱
○神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
○神社コラム・061◆神社の音・参(竜笛)
○神社コラム・062◆神社の音・四(鈴)
こちらもご覧ください。
皆さん神社でお参りをするときに、手を合わせて、ぱんぱんと打ちますよね。
これを柏手(かしわで)と呼びます。

お寺でお参りする時は、合掌(がっしょう)して音をたてませんが、
神社では手を打つのが作法です。
かつては、手を打つことで貴人に対する敬意を表していたのが
神社の拝礼作法として伝わったとも言われています。
手を打つ回数は2回が一般的ですが、出雲大社では4回打つのが作法です。
こちらに関しては過去の記事もご覧ください。
〇神社コラム・008◆出雲大社の四拍手
〇神社コラム・009◆続・出雲大社の四拍手

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・062◆神社の音・四(鈴)
更新:2016/12/1 18:56
神社の音や音楽に関するお話をさせていただいています。
○神社コラム・059◆神社の音・壱
○神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
○神社コラム・061◆神社の音・参(竜笛)
こちらもご覧ください。
今回は鈴の話です。
神社にはいたる所に鈴があります。
お参りをするときには鈴をならしますし、
神殿では巫女が鈴を持って舞い踊ります。
お守りにも鈴がついていることがありますね。
また出雲大社では「しあわせの鈴」をお授けしております。

こうした神社と鈴の関係には、
鈴が「タマフリ」の道具とされていることがあります。
「タマフリ」とは漢字で「魂振り」と書き、
魂を活性化させることを意味しています。
こちらについては以前の巫女舞の記事でも少し触れましたので、
よろしければご覧ください。
神社コラム・045◆舞う巫女のすがた・巫女舞

また鈴の音は場を清める力があるとされます。
一説には「涼しい(すずしい)」と「鈴(すず)」は同じ語源なのだとか。
鈴の音が涼やかさや爽やかさをもたらす、そんなイメージでしょうか。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
○神社コラム・059◆神社の音・壱
○神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
○神社コラム・061◆神社の音・参(竜笛)
こちらもご覧ください。
今回は鈴の話です。
神社にはいたる所に鈴があります。
お参りをするときには鈴をならしますし、
神殿では巫女が鈴を持って舞い踊ります。
お守りにも鈴がついていることがありますね。
また出雲大社では「しあわせの鈴」をお授けしております。

こうした神社と鈴の関係には、
鈴が「タマフリ」の道具とされていることがあります。
「タマフリ」とは漢字で「魂振り」と書き、
魂を活性化させることを意味しています。
こちらについては以前の巫女舞の記事でも少し触れましたので、
よろしければご覧ください。
神社コラム・045◆舞う巫女のすがた・巫女舞

また鈴の音は場を清める力があるとされます。
一説には「涼しい(すずしい)」と「鈴(すず)」は同じ語源なのだとか。
鈴の音が涼やかさや爽やかさをもたらす、そんなイメージでしょうか。
◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
神社コラム・061◆神社の音・参(竜笛)
更新:2016/11/7 16:04
神社の音や音楽に関するお話をさせていただいています。
●神社コラム・059◆神社の音・壱
●神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
こちらもご覧ください。
太鼓などの打楽器のほかに
神社では管楽器も奏でられます。
なかでもよく用いられるものが、龍笛(りゅうてき)と呼ばれる横笛です。
太鼓や篳篥(ひちりき)などの主旋律にあわせて演奏し、曲を装飾します。

龍笛は天と地の間の空を表し、空間を自由に動き回る龍にたとえられます。
またその名の通り、龍の鳴き声とも呼ばれる鋭い音を出す楽器です。
演奏用に七つの穴が開いており、この穴を適宜指でふさぐことで音階を調節します。
また歌口(うたぐち)と呼ばれる息を吹き込むための穴が開いていますが、
ゆるやかに息を吹き込むことで「ふくら」と呼ばれる低い音が、
逆に強く吹き込むことで「せめ」と呼ばれる高い音が出るようになっています。

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
●神社コラム・059◆神社の音・壱
●神社コラム・060◆神社の音・弐(太鼓)
こちらもご覧ください。
太鼓などの打楽器のほかに
神社では管楽器も奏でられます。
なかでもよく用いられるものが、龍笛(りゅうてき)と呼ばれる横笛です。
太鼓や篳篥(ひちりき)などの主旋律にあわせて演奏し、曲を装飾します。

龍笛は天と地の間の空を表し、空間を自由に動き回る龍にたとえられます。
またその名の通り、龍の鳴き声とも呼ばれる鋭い音を出す楽器です。
演奏用に七つの穴が開いており、この穴を適宜指でふさぐことで音階を調節します。
また歌口(うたぐち)と呼ばれる息を吹き込むための穴が開いていますが、
ゆるやかに息を吹き込むことで「ふくら」と呼ばれる低い音が、
逆に強く吹き込むことで「せめ」と呼ばれる高い音が出るようになっています。

◆神社コラム◆
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
この記事を共有する
この記事つぶやく
カテゴリ