カテゴリ
◇故きを温ねて新しきを知る <4>◇
更新:2017/4/6 15:05
ようやく防府では桜が見ごろを迎えそうですが
天気予報では週末は雨。
すこし残念ですね・・・・
さて今日も、日本の結婚式文化についてみてみましょう!
【室町時代の結婚】

武家社会が確立して、「嫁入婚」がだんだん支配的な形式となってきた鎌倉時代ですが
室町時代に入ってからは、各地で反乱などが起こるなど将軍の権威が弱くなってきました
そこで武家が乱れた世を安定させる方策として考えたのが、「礼法」!
民衆へ道徳心を呼び起こす為、様々な「礼法」がつくられました
名家それぞれに「礼法」がつくられ始めましたが、そのなかでも
【小笠原家】と【伊勢家】の力が強く、その二流派の礼法が広まっていったそうです
このうち【伊勢家】は礼法の本もまとめ、「嫁入記」など室町時代の婚礼の基本を作ったと言われいます
このころは禅宗文化の影響を受け、建物も書院造りにかわり「床の間」が家につくられるようになりました
これに合わせて、「礼法」も“玄関での作法”、“案内の作法”、“床の間の飾り方”など…より細かな婚礼作法の規定が加えられていきます
(なかには人の立つ位置、視線の方向、手の位置や、会話の内容なども決められていたそう!)
今と違い、そのころの婚礼は細かな礼法も多く、「婚礼儀式」も1日では終わらないほど複雑だったそうです
…そこまで細かく決められていたら、当時の人も大変だったでしょうね
今の「結婚式」が出来上がるのもまだ先の話
文化はもちろん、その時代の権威がどこにあるかで結婚式の様相は変化していったんですね
歴史が好きな方でしたら、すきな時代の結婚式を勉強して少し取り入れてみてもおもしろいかもしれませんね!
◆防府グランドホテルのフェアはこちらから◆
この記事を共有する
この記事つぶやく
カテゴリ
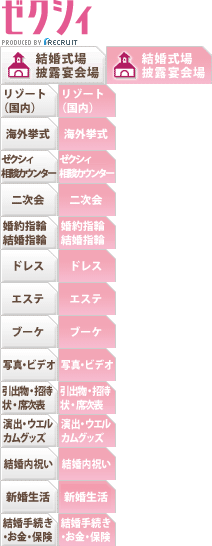




コメントを書く